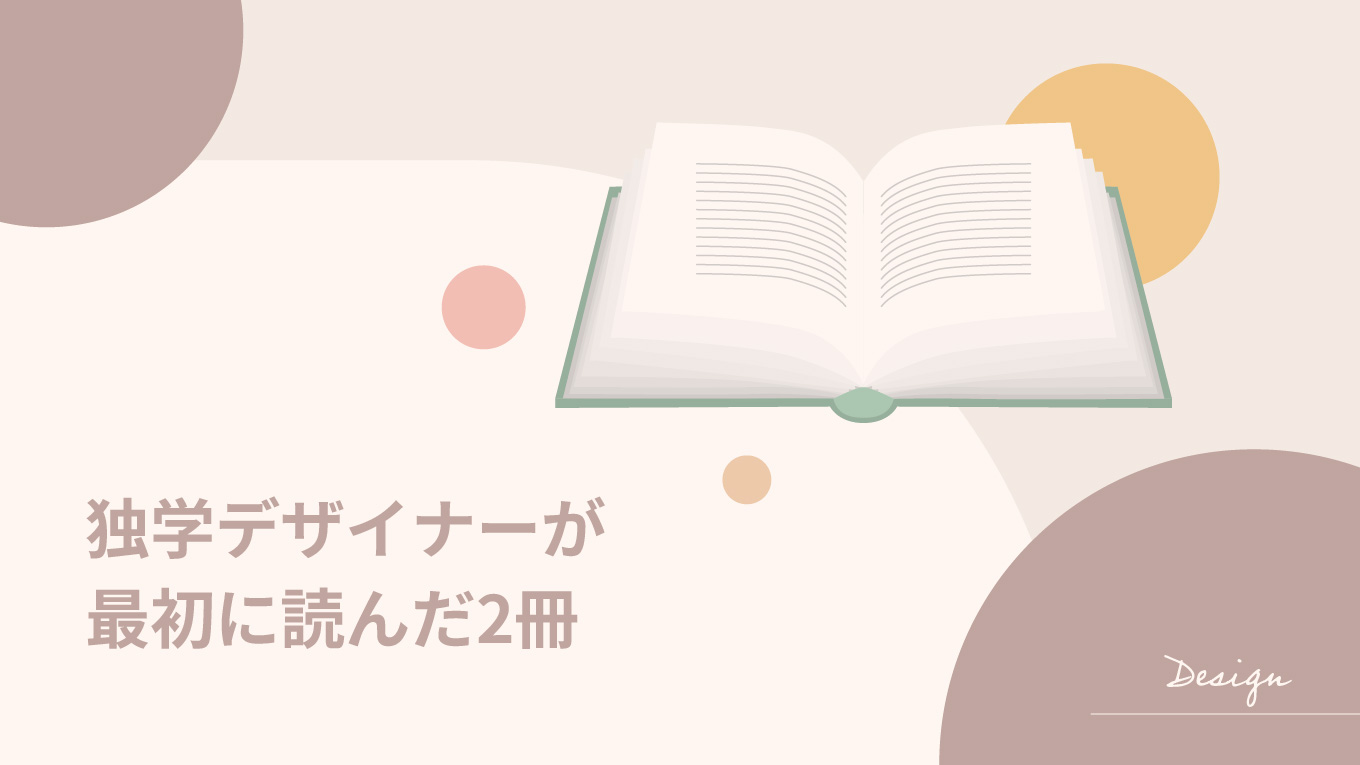色彩と心理で変わるデザインの説得力

- 色を選ぶときは印象やメッセージ性を意識することが大切
- 知識を持って色を選ぶことで、デザインの説得力が上がる
「この色、なんとなくいい感じ」
デザインを始めたばかりの私は、そんな風に色を選んでいました。
でも、あるとき「なぜこの色なんですか?」と聞かれて、何も答えられなかったんです。
この記事では、色選びの不安が減ったきっかけについてお話しします。
色彩と心理を知らずにデザインしていたころ
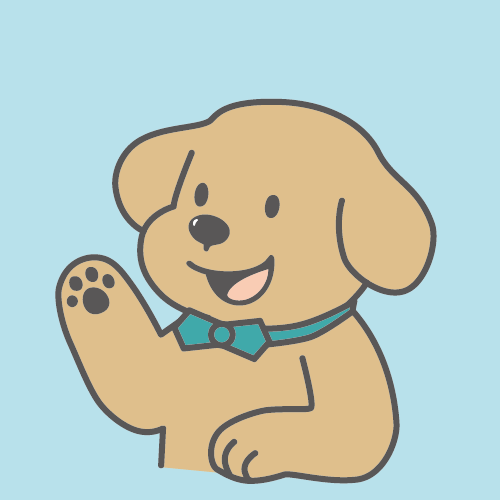
色はフィーリングで決めるモク〜!
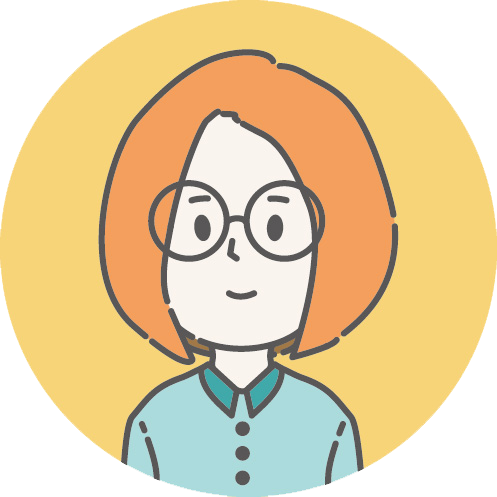
いやいや、それだけじゃ足りないよ〜
デザインを始めたばかりのころ、色を「なんとなく」で選んでいました。
赤は目立つから、青は爽やかだから。そんな感覚的な理由だけです。
でも、あるときクライアントから「なぜこの色なんですか?」と聞かれたとき、うまく答えられませんでした。
「なんとなく…」では説得力がなく、自分でも不安を感じていました。
色彩心理の基本とその奥行き
色には、それぞれ人に与える心理的なイメージがあります。
- 赤=情熱・革命・危険
- 青=誠実・冷静・信頼
こうした色彩心理の基本は、デザインの世界でよく使われます。
ただし、注意したいのは「色の印象は必ずしも普遍的ではない」ということです。
文化や国、地域によって、色の意味は大きく変わることもあります。
文化で変わる色の印象
赤いポストと青いポストの違和感
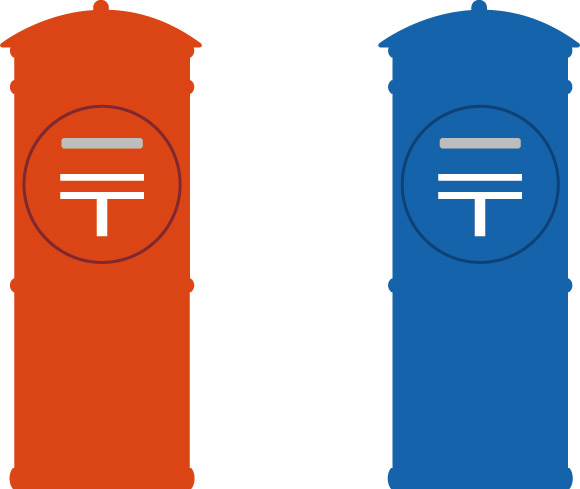
日本では郵便ポストといえば赤がおなじみの色です。
でも海外では、青や黄色のポストが主流の国もあります。
日本では青いポストは少し不思議に見えるように、海外の人にとっては赤のほうが違和感があるかもしれません。
このように、色の持つ印象は文化や経験によっても変わります。
デザインで色を使うときは、受け手の「共通認識」を意識することも大切です。
色彩と心理を学んで変わったこと
色の背景を知ることで、「なぜこの色を選んだのか」を説明できるようになりました。
たとえば、商品パッケージに青を使う場合でも、ただ「爽やかだから」ではなく、「誠実さと清潔感を伝えたいから青を選びました」と根拠を持って話せます。
結果として、色選びに自信がつき、説得力のあるデザイン提案ができるようになりました。
色を決めるときに意識していること
- 受け手の文化や経験を踏まえて色を選ぶ
- 色の歴史的・社会的背景まで意識する
- 見た目の好みよりも「伝えるべき印象」を優先する
- 文字の可読性やアクセシビリティも併せて確認する
色はただの装飾ではなく、メッセージを届ける手段です。
知識を持って選ぶことで、デザインの説得力は確実に上がります。
学びのきっかけになった本
今回の視点をくれたのが『「色彩と心理」のおもしろ雑学/ポーポー・ポロダクション著』です。
色に関する雑学や文化的背景、心理的効果などが事例とともに紹介されていて、読んでいて飽きません。
「この色がなぜこういうイメージなのか?」を知ることで、デザインの引き出しが確実に増えます。 色に説得力を持たせたい方に、ぜひおすすめです。