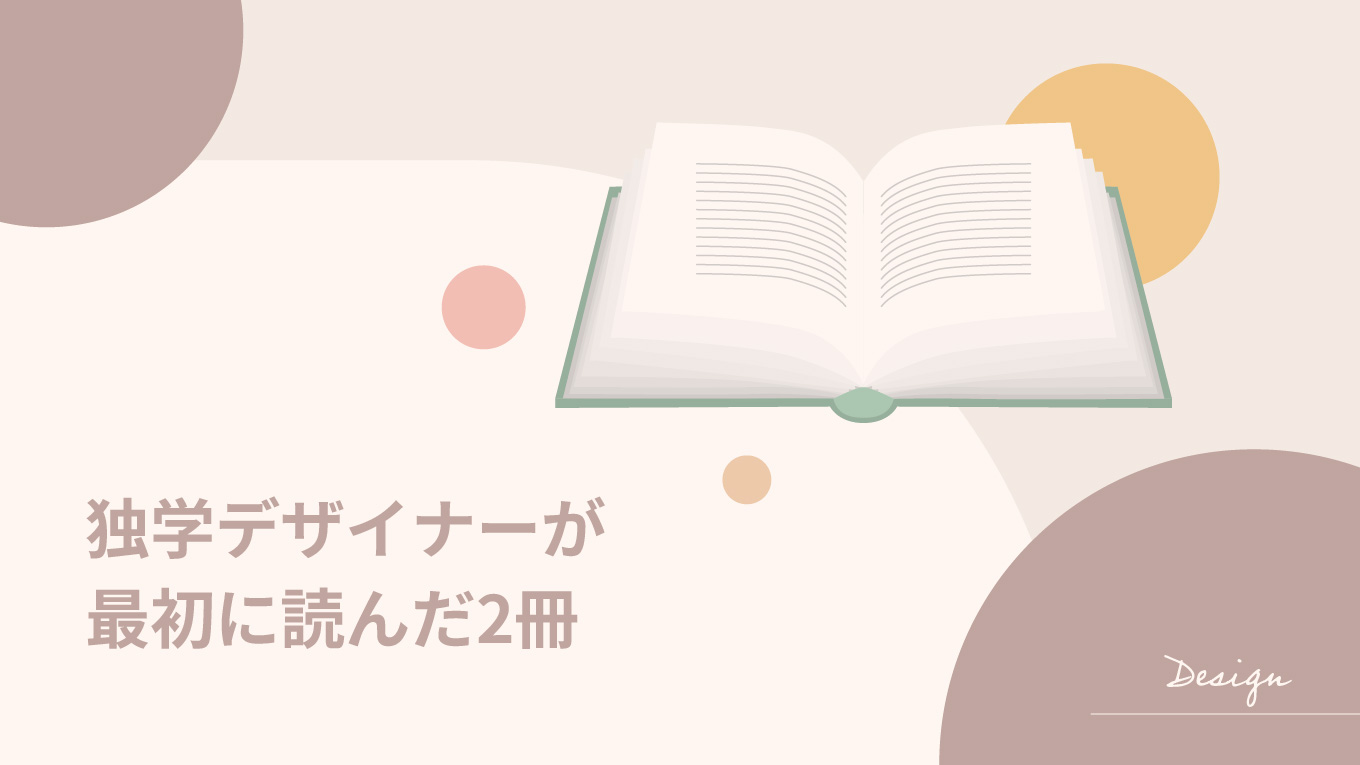フォント選びに迷わない工夫と習慣

- フォント選びで悩むなら、あえて選択肢を絞ってみるのも一つの方法
- シンプルな文字でも、十分に伝わる力がある
フォント選びに悩んでいた私が、「シンプルでも伝わる」ことに気づき、あえて選択肢を絞ることで迷いが減った経験をまとめました。
フォント選びに悩んでいたころの私
種類が多すぎて、毎回迷っていた
デザインを始めたばかりのころ、私はフォント選びにとても時間がかかっていました。
「もっと雰囲気を出したい」「なんとなく違う気がする」
そんな思いで、フォントパネルとにらめっこする日々。
クセのあるフォントを使うと全体のバランスが崩れてしまい、新しい書体を試しても、読みにくかったり、浮いてしまったり。
「これだ!」と思えるフォントがわからず、ただ時間だけが過ぎていきました。
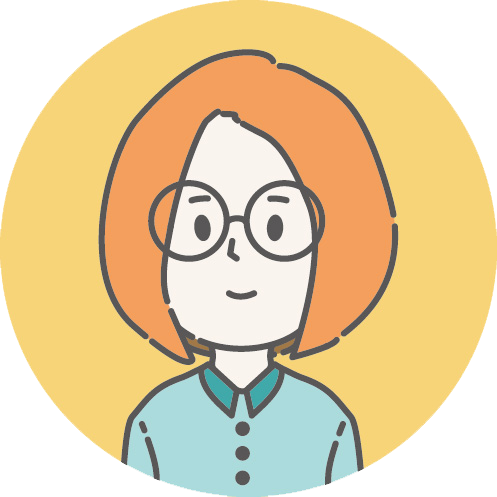
すてきなフォントがありすぎて迷います……
オシャレに見せたい欲が空回り
「センスがよく見えるフォント」を探し回ることに夢中になっていた私。
結果的にまとまりのない仕上がりになって、自分のセンスのなさに落ち込むことも多くありました。
シンプルでも伝わると気づいた転機
シンプルな文字に心を打たれた瞬間
いろいろな本や作品集を眺めていたとき、ふと目に留まったデザインがありました。
使われていたのは、ごくごくシンプルなフォント。
装飾もクセもないのに、驚くほど読みやすく、美しくまとまっていたのです。
そのとき、私は思いました。
「凝ったフォントを使うことだけが、センスの良さではないのかもしれない」
むしろ、伝えたいことが明確なときほど、シンプルな文字のほうがまっすぐ届くのではないか。
そう感じるようになりました。
フォント選びの習慣と工夫
あえて選択肢を狭める
それ以来、私は使うフォントをあらかじめ決めておくようになりました。
無理のない範囲で、次のようなルールを設けています。
- 使用フォントは、よく使われるベーシックなものを中心に3〜5種類まで
- ウェイト(太さ)やサイズで変化をつけて、印象にバリエーションを出す
- アウトライン化は最後の工程まで行わず、柔軟に調整できる状態を保つ
このように、あえて選択肢を絞ることで、迷う時間が減り、「どれを使うか」ではなく「どう伝えるか」に意識を向けられるようになりました。
媒体によって異なるフォントの役割
私は普段、チラシなどの商業デザインを手がけることが多いのですが、そのような媒体ではやはり「読みやすさ」「伝わりやすさ」が何より重要だと実感しています。
一方で、ロゴのように“印象づけ”が主目的のデザインでは話が少し違ってきます。
フォントそのものが表現の主役になったり、独自の加工を加えることで、ブランドらしさを出す必要が出てきます。
フォントの選び方や使い方は、目的によって変わるという感覚も、経験を重ねるなかで少しずつ身についてきました。
シンプルな文字は、想像以上に力を持っている
ポートフォリオサイトや商業デザインを見ていると、意外にもシンプルなフォントが使われている場面が多いことに気づくようになりました。
特にクライアントワークでは、「読みやすさ」や「伝わりやすさ」が何より大切。
凝ったフォントを使うよりも、丁寧に組まれたシンプルな文字の方が、信頼感や誠実さにつながるケースが多いと感じています。
フォント選びに悩むあなたへ
「選択肢を減らす」ことも、ひとつの解決策
もし今、フォント選びで迷っているなら、あえて「選ばない工夫」をしてみるのもひとつの方法です。
フォントパネルの前で悩んでいた時間が、「どう伝えるか」を考える時間へと変わっていきます。
ユニークなフォントは使いこなしてこそ
もちろん、世界観を強く打ち出したいときには、ユニークなフォントが大きな力を発揮する場面もあります。
ただ、それを活かすには、全体のバランスを見る力や、フォントへの深い理解が必要だと感じています。
最近では、フォントのアレンジや文字加工といったさらに深い表現の技法にも少しずつ挑戦中です。
フォント選びの世界は、想像以上に奥が深い。
私自身も、今なお学びの途中です。
あなたのフォント選びが、少しでも楽しく、ラクになるきっかけになればうれしいです。