独学デザイナーが最初に読んだ2冊
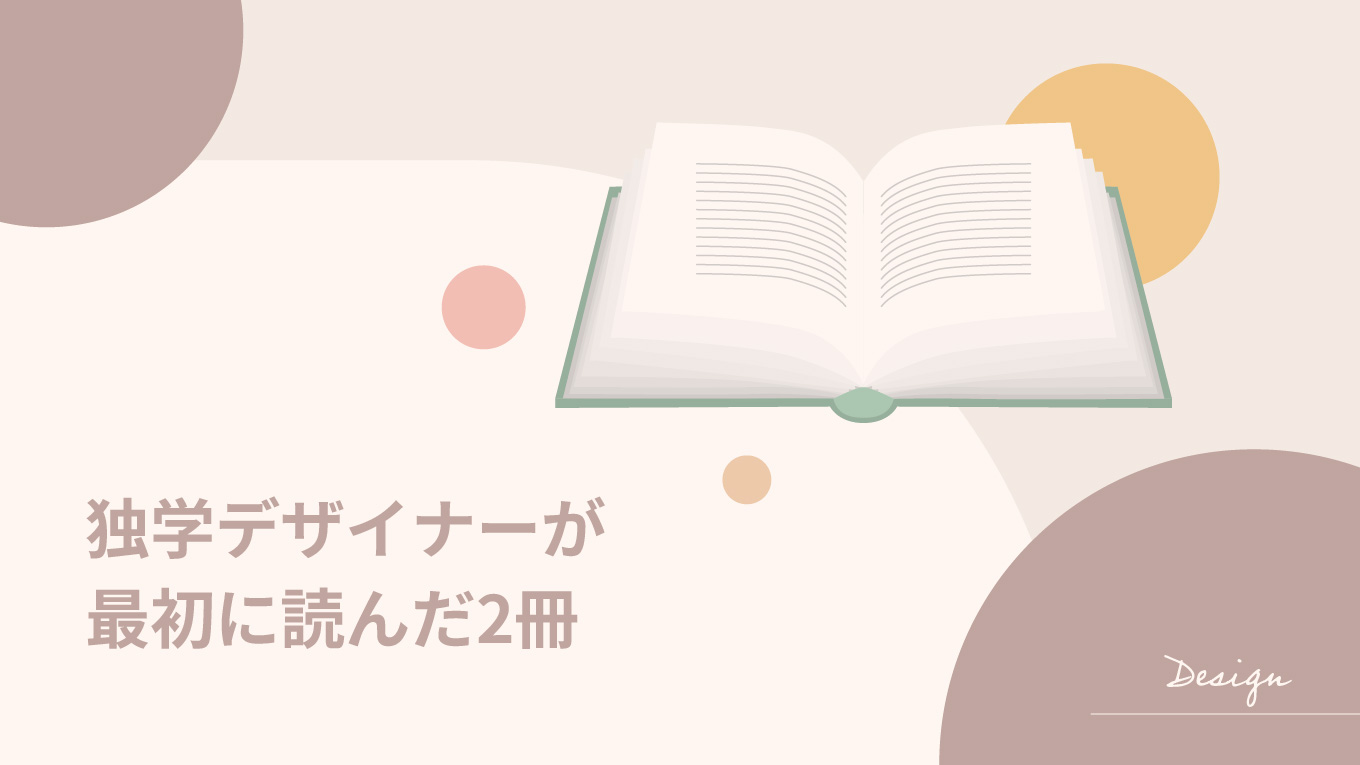
- 基礎を学ぶことで、自信を持ってデザインに取り組める
- センスは生まれつきではなく、知識と経験の積み重ねで育つ
独学でデザインを始めたころ、「センスがない」と悩み、何を学べばいいのかも分からずに手を動かしていました。
そんな私を支えてくれたのが、
『デザイン 知らないと困る現場の新常識100』と
『デザイン、現場の作法。デザイン力を鍛える仕事術』という2冊の本です。
この記事では、私がこの本から得た気づきと、今も大切にしている考え方をご紹介します。
この本を手に取ったきっかけ
とにかく基礎を幅広く知りたかった
独学でデザインを始めたばかりの私は、何から学べばいいのか分からず、不安を抱えながら手を動かしていました。
そこで、まずは基礎を広く知ろうと、本を探しました。
体系立った学びの道筋を示してくれるものが欲しかったのです。
何もかも足りないと感じていた時期
当時は「センスがない」と思い、頭の中のイメージを形にできず、似たようなデザインばかり。
さらに何の準備もないまま現場に放り込まれ、必死で食らいつく日々でした。
だからこそ、今すぐ役立つ知識と考え方が必要だったのです。
私の基礎となった2冊
以下に紹介する2冊は、どちらもデザインや印刷の現場、主要アプリケーションについて幅広く解説した本です。
レイアウトや色使いの基本から、入稿データの作り方、印刷工程の流れまで、独学ではなかなか知る機会のない知識が網羅されています。
「いま困っていること」と「将来きっと役立つこと」の両方が詰まっていて、安心して読み進められる内容でした。
単なるテクニック集ではなく、現場での実践に直結する考え方や注意点がまとまっていて、読みながらすぐに仕事に活かせました。
何も武器がない状態から「まず何を知っておくべきか」の地図をくれた2冊です。
『デザイン 知らないと困る現場の新常識100』
まず手に取ったのが、この『デザイン 知らないと困る現場の新常識100』。
当時の私にとって、まさに「現場で生き残るための教科書」でした。
最初はひたすらインプットに専念。
特に印象に残っているのは、印刷の解像度に関する内容です。
独学で作った初めての納品データが重すぎて開けないと言われ、理由も改善方法もわからなかった私に、この本が明快な答えをくれました。
解像度の基本や適切な設定、用途ごとの使い分けが理解でき、「だから開けなかったのか!」と納得。
知っているか知らないかで、現場のトラブルは大きく変わると実感しました。
『デザイン、現場の作法。デザイン力を鍛える仕事術』
一方、『デザイン、現場の作法。デザイン力を鍛える仕事術』は、デザインにまつわる実践的なマナー本です。
仕事の進め方や考え方、クライアントやチームとの関わり方など、仕事への向き合い方の勉強になりました。
「どうすれば相手が安心して依頼できるデザイナーになれるか」
「トラブルを未然に防ぐために、どんな準備や確認が必要か」
そんな現場の作法が具体例とともに書かれており、独学では気づけない部分を知ることができ、安心感につながりました。
今はこう考えてデザインしている
「伝えるために整える」という意識
この2冊から得た知識と視点で、私のデザインの捉え方は大きく変わりました。
ただ見た目を整えるのではなく、「伝えるために整える」ことがデザインの役割だと考えるようになったのです。
色やフォント、余白やレイアウトも、すべては情報をスムーズに届けるための手段。
迷ったときの判断軸がはっきりしました。
センスより思考を積み重ねる大切さ
以前は「センスがない」と悩んでいましたが、今ではセンスは知識と経験の積み重ねで育つものだとわかります。
日々観察し、考え、試すこと。
その繰り返しが、自分なりのデザインを作る力になっています。
大丈夫、少しずつ積み上げていけばいい
現場に放り込まれて必死に食らいついていたあの頃、この2冊は私に安心と方向性をくれました。
今でも行き詰まったときや初心を思い出したいときに読み返しています。
もし今、あなたが「センスがない」「何から学べばいいかわからない」と感じているなら、焦らなくても大丈夫です。
気になるところや興味のある分野からで構いません。
少しずつでも学び続ければ、必ず前に進めます。




